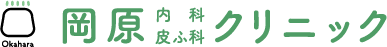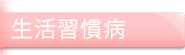C型慢性肝炎(2型)に有効な新薬(ソバルディ)が発売されました。
C型慢性肝炎(2型)に有効な内服薬(ソバルディ)が2015年6月10日より使用可能となりました。ソバルディは2型のC型慢性肝炎(代償性肝硬変を含む)に対して、経口剤のみによる12週間治療を可能にします。リバビリン*との併用により高い治療成功率を示しました。(*リバビリン;作用機序は不明であるが、インターフェロンなどと併用することにより抗ウィルス効果を発揮する内服薬。)

C型肝炎の新しい治療薬(ダクルインザ錠+スンベプラカプセル)の適応が
拡大しました
2014年10月より、C型肝炎(1型)の新しい治療薬(ダクルインザ錠+スンベプラカプセル)が公費助成の対象となりましたが、再燃・再発例では使用できませんでした。
2015年3月20日より、すべての1型のC型慢性肝炎(代償性肝硬変を含む)の患者様に処方できることとなりました。これにより従来の治療法と比べて治療成功率が高く、副作用の少ない治療法が多くの方々に適応されることとなります。
これまでインターフェロン治療後に再発や再燃された患者様、インターフェロン治療の副作用が心配で治療を控えておられた方は、この新しい治療法について検討されてみてはいかがでしょう。

C型肝炎ウィルスの型について
C型肝炎ウィルスは4つの型(1a、1b、2a、2b)の4つに分類されます。最も多いのは1b型で70%、2a型が20%、2b型が10%程度で1a型はほとんど見られません。1b型は日本人で最も多い型ですが、インターフェロン治療が効きにくく、再発や再燃が多くありました。

ソバルディ+リバビリン治療の臨床成績
- 治療成功率
- 97.1%(従来の治療法:77.6%)
従来の治療法;ペグインターフェロン/リバビリン併用療法 - 副作用
- 貧血(11.4%)
頭痛(5.0%)、倦怠感(4.3%)、悪心(4.3%)、掻痒症(4.3%)など

ソバルディ+リバビリン治療の実際
- 対象
- セログループ(ジェノタイプ)2型のC型慢性肝炎またはC型代償性肝硬変
- 薬剤
- ソバルディ錠、リバビリン錠
- 投与期間
- 12週
- 禁忌
- 妊婦、授乳婦、同系薬剤過敏症の既往、重度の心疾患・腎障害・肝障害・精神疾患、自己免疫性肝炎、異常ヘモグロビン症
- 併用禁忌
- リファンピシン、カルマバゼピン、フェニトイン、セイオウオトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)含有食品
- 併用注意
- リファブチン、フェノバルビタール、抗HIV薬、アザチオプリン
注意1 飲み忘れにより、期待される効果が得られない場合あり。飲み忘れに注意。

ダクルインザ+スンベプラ治療の臨床成績
- 治療成功率
- 89.1% (従来の治療法:62.2%)
従来の治療法;インターフェロン/リバビリン+テラプレビル併用療法 - 副作用
- 鼻咽頭炎、頭痛、発熱、下痢など軽症なもの:10~36%
肝機能障害(AST、 ALT上昇):16%
重篤なもの5%(死亡:0%、投与中止:5%)

ダクルインザ+スンベプラ治療の実際
- 対象
- セログループ(ジェノタイプ)1型のC型慢性肝炎またはC型代償性肝硬変
- 薬剤
- ダクルインザ錠、スンベプラカプセル 体内のHCVに直接作用し、減少させる薬
- 投与期間
- 24週間
- 禁忌
- 中等度以上の肝機能障害、妊婦(妊娠可能性のある婦人)、授乳中の方 以下の薬を内服中の方(リファンピシン、リファブチン、フェニトイン、カルバマゼピン、フェノバルビタール、デキサベタゾン全身投与、セイヨウオトギリソウ(St. John’s Wort、セント・ジョーンズ・ワート)含有食品、アゾール系抗真菌剤(経口または注射剤)、クラリスロマイシン、エリスロマイシン、ジルチアゼム、ベラパミル塩酸塩、コビシスタットを含有する製剤、HIVプロテアーゼ阻害剤、モダフィニル、非ヌクレオシド系逆転写酵素阻害剤(リルピビリン塩酸塩を除く)、ボセンタン水和物、シクロスポリン、フレカイニド、プロパフェノン)
- 注意1
- 飲み忘れにより、期待される効果が得られない場合あり。飲み忘れに注意。
- 注意2
- 肝機能障害など副作用が現れることあり。定期的検査を要す。
※ 臨床成績は「インターフェロンを含む治療法に適格の未治療患者及び前治療再燃患者を対象とした国内第3相試験(AI 447031試験)」より引用。

肝炎ウィルス検査について
体が疲れやすい、休息後も疲労感が残るという症状がおありの方は、一度血液検査を受けていただければと思います。もし血液検査で肝機能の数値が上昇していれば、肝炎ないし肝機能障害があるということになります。肝炎(肝機能障害)の原因としてウィルス性(C型肝炎、B型肝炎)とそうでない場合で治療方針が変わってきます。
ウィルス性肝炎の治療法には、体からウィルスを排除する抗ウィルス療法と、肝庇護剤による肝臓を保護する治療があります。ウィルス性肝炎は輸血や入れ墨など、針を介した行為や性交で感染するといわれていますが、いつ感染したのかわからないこともあります。早めに診断をして肝硬変や肝臓癌の予防につなげていくことが大切です。
広島県ではいままでに肝炎ウィルス検査を受けたことがない人を対象に、無料でB型肝炎とC型肝炎の検査を実施しています(広島市では20歳以上の人に限定)。
当院は広島県と委託契約を結んでおり、無料で検査を行うことができます。
卒業や就職などの節目に、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

胆石症について
胆汁が胆嚢や胆管の中で、砂状となりそれが固まったものが結石です。
胆石があっても、胆嚢や胆管内で浮遊した状態であれば症状はありません。
胆石が胆嚢や胆管の出口に詰まったとき(嵌頓)、急激に右わき腹~背中にかけて高度の痛みが生じます。焼肉などの高脂肪食+アルコールが原因で胆石が嵌頓し、夜間急性胆嚢炎を発症される方もおられます。

逆流性食道炎について
心窩部から胸部の不快感、酸の逆流、胸焼けを呈します。
胸部の症状は強く、心臓の痛みと間違えられるほどです。
有効な治療薬がありますが、漫然と服薬を継続せず、年に1度は食道癌などの悪性疾患を除外するために、胃カメラやバリウム検査といった画像診断を受けることをお勧めします。

胃・十二指腸潰瘍について
心窩部から季肋部にかけての持続的な鈍痛が典型的な症状です。潰瘍の場所によっては、背中の痛みとして現れることもあります。十二指腸潰瘍では食事により痛みが和らぐこともあります。
ストレス、ピロリ菌、痛み止めの薬などが原因とされています。
治療は酸分泌抑制薬が主体です。ピロリ菌感染を伴っている場合は除菌療法を行います。

腸炎・下痢について
- ● 感染性胃腸炎
- 細菌やウィルスの腸管からの感染が原因で下痢・腹痛・嘔吐が主症状となります。悪化すると、脱水症や菌血症による発熱、全身状態悪化から腎不全や血圧低下に至ることもあります。
- 症状
- 通常急性に発症し、大部分は1週間以内に軽快します。夏はカンピロバクター、病原性大腸菌、黄色ブドウ球菌など細菌が多く、冬はノロウィルス、ロタウィルスなどウィルスが原因となることが多いです。アジア、アフリカなど海外旅行からの帰国前後に発症する場合は、赤痢やコレラなどの感染も考慮します。
- 診断
- 腹痛や下痢回数、便の状態を聞きます。次いで原因菌(ウィルス)との接触機会や加熱が不十分な食品や外食などのエピソードも詳しく聞きます。最終的には便培養検査(細菌感染)や便中抗原検査(ノロウィルス)で診断を確定します。
- 治療法
- まずは脱水状態の改善、次に腸管の安静を保つことです。細菌感染を強く疑う場合には、培養結果を待たずに抗菌剤の処方をすることもあります。下痢止めは菌(ウィルス)の体外への排出を遅延させるため、なるべく使用せずに経過を見ていきます。水分や食事がとれないほどの重症下痢の場合には、点滴や短期間の入院が必要となることもあります。
- 注意
すべきこと - 細菌(ウィルス)は保菌者の便や唾液経由で他人に感染していきますので、衣類や床が便や唾液、吐物で汚染した場合は塩素系漂白剤で殺菌したのちに、ほかの人と一緒に洗濯をするようにしてください。また排便後の石鹸手洗いは言うまでもありません。 塩素系漂白剤による殺菌については、「トップページ」→「内科」下段の「ノロウィルスの感染予防について」をご参照ください。
- ● 慢性腸炎
- 慢性的な下痢や便秘を起こす病気としてストレスが原因で消化管の運動と知覚障害による過敏性腸症候群と消化管の免疫系の異常が原因の炎症性腸疾患に分けられます。
- ● 過敏性腸症候群
- 消化管運動をつかさどる神経は自律神経で自分の意思と無関係に食物の消化、吸収、排せつを行っています。ストレスのない状態では、食物は胃酸で分解され、吸収されやすい形となり、小腸でタンパク質や脂肪など栄養分を吸収され、大腸で水分を吸収され丁度よい硬さの便が排出されます。口から肛門まで通常1~2日間で、個人差はありますが通常1日1~2回の排便が正常です。
ところが、強いストレスを受けた時や、ストレスを感じやすい体質の方の場合、自律神経に影響を及ぼし、下痢や便秘、腹痛といった消化管運動の障害を起こすことがあります。
根本的な治療法はストレスのコントロールですが、消化器内科ではまず、食事やライフスタイルの改善により、自律神経や消化管に負担をかけないような習慣作りをご指導させていただき、症状に応じて薬を処方していきます。 - ● 炎症性腸疾患について
- 免疫系の異常のために、慢性的に腸で炎症がおこり下痢や血便、腹痛などが何週間にもわたり続きます。
潰瘍性大腸炎とクローン病が代表的な疾患です。好発する年齢層としては10~20代と40~50代に2つのピークがあります。近年の食事の欧米化のためか患者数は年々増加しています。5-ASAと免疫反応を抑制する薬(ステロイドや免疫抑制薬)が治療の中心ですが、食事中の動物性脂肪を減らし、ストレスを減らすことも大切なことです。
1日5回以上の下痢や血便が続く場合、早めに専門医で診察をうけるべきと思われます。

便秘について
- ● 診断
- 健常者の排便回数は1日3回~1週間に数回と幅があります。通常3日間排便がない場合を便秘と診断することが多い。
- ● 慢性腸炎
- 慢性的な下痢や便秘を起こす病気としてストレスが原因で消化管の運動と知覚障害による過敏性腸症候群と消化管の免疫系の異常が原因の炎症性腸疾患に分けられます。
- ● 生理
- 盲腸で液体状の便は大腸で水分が吸収されながら、蠕動運動で直腸まで送られます。直腸に便が到達すると直腸壁の進展により便意が生じ排便が促されます。
- ● 分類
- 便秘症は弛緩性便秘、痙攣性便秘に大別されます。
- 弛緩性便秘
- 大腸の蠕動運動の低下により便が大腸内で停滞した状態です。日本人では高齢の女性に多く、また何らかの疾病や外傷で長期臥床状態の方にもよく見られます。便秘は持続的で便意が少なく、腹痛を伴わないことが多いです。治療法としては、刺激性下剤を使用し、塩類下剤を併用します。漢方薬や高分子重合体、腸管運動調整薬が有効なこともあります。
- 痙攣性便秘
- ストレスや不規則な食生活により大腸がけいれん性の収縮を生じ、蠕動運動が障害された状態です。便の移動が妨げられ硬い便が形成されます。便はウサギの糞のような兎糞となり、便意は間欠的で腹痛を伴います。治療法としては、生活習慣の改善、食後の運動など生活指導を行い、腸管運動調節薬を処方します。

その他の便秘症
- 直腸性便秘
- 排便を我慢することを繰り返すことにより生じます。治療法は朝食後の排便習慣の励行、食後の運動を基本に直腸を刺激する坐剤を使用することもあります。
- 器質性便秘
- 腹部の手術後の癒着や腸管の炎症や捻転、腫瘍などが原因の物理的な便の通過障害です。数日~数週間で症状が生じた場合には、大腸の内視鏡検査や腹部CTなど大腸がんや腸ねん転などの除外診断が必要となります。腹部手術後の慢性的な便秘に対しては有効な漢方薬があります。
- 食事性便秘
- 食物繊維の少ない偏った食事や小食が原因で生じます。治療法としては食物繊維の豊富な食事を十分に摂っていただくことです。

便秘と漢方薬
- 弛緩性便秘
- 大黄甘草湯、桃核承気湯、麻子仁丸など大黄を含む薬がよく使われます。
大黄甘草湯は大黄と甘草からなる誰にでも使える下剤ですが、効果がシャープなため効きすぎに注意が必要です。
桃核承気湯は女性のイライラやのぼせ、ニキビなど月経関連の症状にも有効です。麻子仁丸は高齢者や虚弱体質の方(便がコロコロ)に有効で、効き方はマイルドです。 - 痙攣性便秘
- 芍薬を含む桂枝加芍薬大黄湯、桂枝加芍薬湯などがよく使われます。
芍薬は消化管の攣縮を緩める作用があります。
芍薬を含む薬としては効果の強い順に桂枝加芍薬大黄湯、桂枝加芍薬湯、小建中湯、腸潤湯となります。体力のある人は強い薬、高齢者や弱々しい人は弱めの薬から処方します。
イライラ、自律神経失調気味の女性の方には、更年期障害や月経困難にも有効な加味逍遥散が使われます。 - 外科周術期や腸閉塞予防、治療
- 大黄を含まない大建中湯がよく使われます。大建中湯は術後以外にも体力が低下した人で、腹が冷え、腹部膨満のある方に有効です。